この記事で分かること
・子会社化の狙い:遺伝子解析技術を強みとし、がんなどの疾患を対象とした遺伝子診断サービスを展開するDNAチップ研究所を活かし、検査・診断領域での新事業創出を目指しています。
・肺がんコンパクトパネルとは:非小細胞肺癌(NSCLC)の治療において、特定の遺伝子変異を検出し、適切な分子標的薬の選択を支援するための診断システム
・がん遺伝子の変異解析の重要性:変異の解析によって、最適な治療薬の選択や治療効果の予測の高精度化、免疫療法の有効性などが可能となり、がん治療をより効果的かつ個別化できる。
三井化学によるDNAチップ研究所の子会社化
三井化学株式会社は、2025年4月8日に株式会社DNAチップ研究所の普通株式を公開買付け(TOB)を終了し、同社を完全子会社化したことを発表しました。
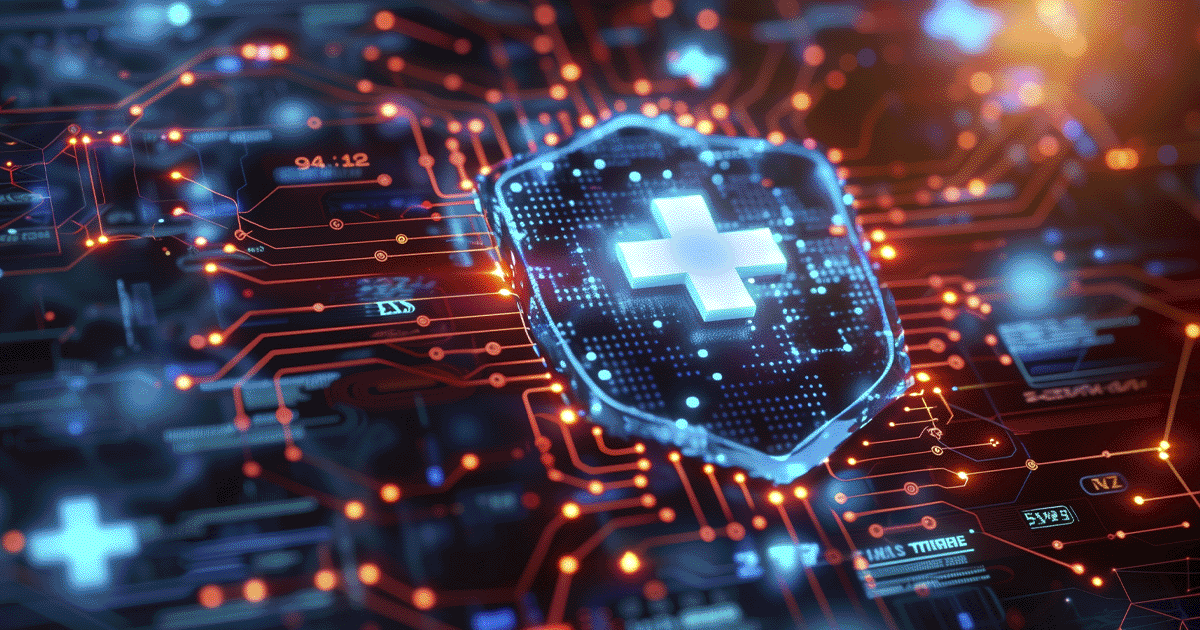
三井化学は、長期経営計画「VISION 2030」において、ライフ&ヘルスケア・ソリューション事業を成長領域の一つとして位置付けています。
DNAチップ研究所は、遺伝子解析技術を強みとし、がんなどの疾患を対象とした遺伝子診断サービスを提供しています。両社は2023年1月に資本業務提携契約を締結し、協力関係を築いてきました。
今回の完全子会社化により、三井化学はDNAチップ研究所の経営資源を効率的かつ積極的に活用し、検査・診断領域での新事業創出を目指しています。
DNAチップ研究所とはどんな会社なのか
株式会社DNAチップ研究所は、1999年4月に神奈川県横浜市で設立された企業で、遺伝子解析技術を活用した研究受託サービスや診断事業を展開しています。
事業内容
- 研究受託事業: 次世代シークエンサーやマイクロアレイを用いた遺伝子発現解析、エクソーム解析、メチレーション解析など、多様な遺伝子解析サービスを提供しています。
- 診断事業: 肺がん組織遺伝子変異検査「肺がんコンパクトパネル」や関節リウマチ薬剤効果予測、うつ病診断技術の開発など、疾患の診断や治療効果予測に関するサービスを展開しています。
沿革の一部
2004年3月に東京証券取引所マザーズ市場へ株式上場し、2014年8月には同取引所第二部へ市場変更しました。
2022年10月、神奈川県川崎市にメディカルラボラトリーを設立し、2024年10月には同市に事務所を移転しています
同社は、「創造的革新」をモットーに、「世の中に役立つこと」「人間尊重」を経営理念として掲げ、ライフサイエンス分野での技術革新と社会貢献を目指しています。

DNAチップ研究所は、遺伝子解析技術を活用した研究受託サービスや診断事業を展開しています。
シークエンサーとは何か
シークエンサー(sequencer)とは、DNAやRNAなどの塩基配列(A, T, G, C)を読み取るための装置です。つまり、「遺伝情報の文字列を解読する機械」と考えてもらうとわかりやすいです。
【もう少し詳しく】
DNAはA(アデニン)、T(チミン)、G(グアニン)、C(シトシン)の4つの塩基からできていて、その並び順(配列)が生物の遺伝情報を決めています。シークエンサーは、この並び順を高速かつ正確に読み取る技術・装置です。
【主なシークエンサーの種類】
- Sanger法シークエンサー(第1世代)
- 古くからある手法で、精度は高いけど処理速度が遅く、大規模解析には向きません。
- 次世代シークエンサー(NGS: Next Generation Sequencer)
- 数百万〜数十億のDNA断片を一度に読み取れる高速装置。
- 医療・創薬・微生物解析・がん研究などで広く使われています。
- 第3世代シークエンサー
- より長いDNA鎖をリアルタイムで読む技術(例:Oxford Nanopore や PacBio)。
- 構造変異の検出や、ゲノムのギャップを埋める研究に活用。
【どんなところで使われている?】
- がんの遺伝子変異解析
- 感染症(例:新型コロナウイルス)の変異追跡
- 先天性疾患の診断
- 個別化医療(遺伝子に基づく治療方針決定)
- 微生物や環境DNA解析

シークエンサー(sequencer)とは「遺伝情報の文字列を解読する機械」であり、遺伝子の変異の解析や先天性疾患の診断などに利用されています。
肺がんコンパクトパネルとは何か
肺がんコンパクトパネル® Dxマルチコンパニオン診断システムは、非小細胞肺癌(NSCLC)の治療において、特定の遺伝子変異を検出し、適切な分子標的薬の選択を支援するための診断システムです。
特徴
・複数の遺伝子へにの検出が可能:EGFR遺伝子変異、ALK融合遺伝子など
・高感度な検出能力: 解析する遺伝子を小グループ(モジュール)に分けて深度の高いシーケンス解析を行うことで、検出感度1%を実現しています。
・多様な検体への対応: 未染スライド(FFPE)検体に加え、気管支ブラシ擦過診(TBB)や針洗浄液(TBNA)などの細胞診検体でも検出が可能です。
・モジュール構造による拡張性: 新たなドライバー遺伝子変異の検出を追加する際、既存の検査精度に影響を与えずに新規ターゲットを追加できる設計となっています。

肺がんコンパクトパネルは、非小細胞肺癌(NSCLC)の治療において、特定の遺伝子変異を検出し、適切な分子標的薬の選択を支援するための診断システムで検出感度の高さや豊富な検体への対応が可能などの特長をもっています。
がんの遺伝子変異解析を行う理由
がんの遺伝子変異解析を行う理由は、以下のようにがん治療をより効果的かつ個別化(パーソナライズ)するためです。
1. 治療薬の選択に役立つ(コンパニオン診断)
がん細胞に特定の遺伝子変異があると、それに対応する分子標的薬が効くことがあります。
たとえば:
- EGFR遺伝子変異があれば → EGFR阻害薬(ゲフィチニブなど)
- ALK融合遺伝子があれば → ALK阻害薬(クリゾチニブなど)
→ 適切な薬を選ぶことで、副作用を減らしながら高い効果を得られます。
2. 治療効果や予後の予測
ある遺伝子変異があるがんは再発しやすい、進行が早いなどの特徴を持つことがあります。
→ 予後(病気の見通し)や治療方針を立てる参考になります。
3. 免疫チェックポイント阻害薬が効くかどうかの判断
たとえば、高頻度マイクロサテライト不安定性(MSI-High)や高腫瘍変異負荷(TMB-High)といった情報があると、免疫療法が効く可能性があります。
4. 新薬の臨床試験(治験)に参加するため
治験は特定の遺伝子変異を持つ患者に限定して行われることが多いため、遺伝子情報が必要になります。
5. がんのタイプや由来の特定(診断補助)
原発不明がんや転移がんの場合、遺伝子情報から「どこから来たがんなのか?」を推定する手がかりになることもあります。

遺伝子変異を特定することで、最適な治療薬の選択や治療効果の予測の高精度化、免疫療法の有効性などを行うことができ、がん治療をより効果的かつ個別化(パーソナライズ)することが可能です。
免疫チェックポイント阻害薬とは何か
免疫チェックポイント阻害薬(Immune Checkpoint Inhibitors)とは、がん細胞による「免疫のブレーキ」を解除し、体の免疫細胞(主にT細胞)ががんを攻撃できるようにする薬です。
■ そもそも「免疫チェックポイント」とは?
私たちの体の免疫システムには、「攻撃のしすぎを防ぐためのブレーキ機構」があります。
それが「免疫チェックポイント」と呼ばれる仕組みです。
代表的な免疫チェックポイント:
- PD-1(Programmed Death-1)
- PD-L1(そのリガンド)
- CTLA-4(Cytotoxic T-Lymphocyte Antigen-4)
がん細胞は、これらを“悪用”して、免疫の攻撃から逃れるのです。
■ 免疫チェックポイント阻害薬の仕組み
この“ブレーキ”を外すことで、
- 免疫ががん細胞を再び認識・攻撃できるようになります。
代表的な薬剤と標的
| 薬剤名 | 標的分子 | 商品名(一例) |
|---|---|---|
| ニボルマブ | PD-1 | オプジーボ |
| ペムブロリズマブ | PD-1 | キイトルーダ |
| アテゾリズマブ | PD-L1 | テセントリク |
| イピリムマブ | CTLA-4 | ヤーボイ |
■ 使われるがんの例
以下のがん種などで使用されています:
- 非小細胞肺がん
- メラノーマ(皮膚がんの一種)
- 腎細胞がん
- 胃がん
- 食道がん
- MSI-Highの大腸がん など
■ メリット・デメリット
メリット:
- 長期効果が期待できるケースがある(“治癒的”な効果も)
- 他の薬が効かないがんに有効なことも
デメリット:
- 効く人と効かない人がいる(=バイオマーカー検査が大事)
- 免疫が正常な組織も攻撃してしまう副作用(免疫関連有害事象:irAE)がある
- 例:肺炎、腸炎、甲状腺炎、糖尿病など

免疫チェックポイント阻害薬とは、「免疫のブレーキ」を解除し、体の免疫細胞(主にT細胞)ががんを攻撃できるようにする薬です。


コメント