この記事で分かること
- 蛍光分析とは:物質に励起光を当てた際に放出される蛍光を利用し、微量な成分の種類(定性)や量(定量)を高感度・高選択的に測定する分析手法です。
- 感度が高い理由:シグナルをゼロベースから検出し、励起光と異なる蛍光の波長を利用して励起光(ノイズ源)を遮断できるため、高感度になります。
- 測定できる分子の例:蛍光分析で励起光を吸収し、蛍光を発する物質を蛍光団とよび、蛍光団の多くは、電子が非局在化している共役二重結合を多く持つ芳香族化合物や複素環化合物です。
蛍光分析
機器分析とは、化学反応を用いる古典的な化学分析に対し、物質が持つ物理的・化学的性質を精密な機器で測定し、その物質の成分や構造を分析する方法の総称です。
高感度で迅速な分析が可能であり、微量な成分や複雑な混合物も精度高く分析できるため、現代の科学技術分野で広く利用されています。
今回は蛍光分析に関する記事となります。
分光分析とは何か
分光分析は、光と物質の相互作用を測定する手法です。紫外可視分光光度法で濃度、赤外分光法で構造、原子吸光分析法で金属元素の定量、蛍光X線分析法で元素組成、核磁気共鳴分光法で分子構造の解析など、使用する光の種類や原理によって多岐にわたります。
蛍光分析とは何か
蛍光分析とは、物質に特定の波長の光(励起光)を照射した際に、その物質がより長い波長の光(蛍光)を放つ現象を利用して、物質の定性(どのような物質か)や定量(どれくらいの量含まれているか)を行う分析手法です。
原理
- 励起 (Excitation):
- 分析対象の分子(蛍光団)が、特定の波長(通常は紫外〜可視光線)の励起光を吸収します。
- これにより、分子内の電子が基底状態 (S0) からエネルギーの高い励起一重項状態 (S1, S2…) へと遷移します。
- 緩和 (Relaxation) と蛍光 (Fluorescence):
- 励起状態になった電子は非常に不安定です。
- 通常、熱としてエネルギーを失い、すぐに最も低い励起一重項状態 (S1) へと遷移します(非放射失活、項間交差)。
- このS1状態から基底状態 (S0) へ戻る際に、余分なエネルギーを光として放出します。この放たれる光が蛍光です。
- 蛍光は励起光よりも必ず長い波長(低エネルギー)を持ちます。これは、励起状態から基底状態へ戻る前に一部のエネルギーが熱として失われるためです(ストークスシフト)。
- この一連のプロセスは非常に短時間(通常 10-9から 10-6秒)で起こります。
特徴
| 特徴 | 説明 |
| 高感度 | 蛍光は励起光を「バックグラウンド」としないため、微量な物質でも極めて高感度に検出できます。 |
| 高選択性 | 物質によって励起光の波長と蛍光の波長が異なるため、特定の物質のみを選んで分析できます。 |
| 非破壊的 | 試料を破壊することなく測定できます。 |
| 環境の影響 | 温度やpH、周囲の分子(クエンチャー)の存在など、環境の影響を受けやすいという側面もあります。 |
応用分野
- 生命科学・医学: DNA、タンパク質、細胞内の特定の分子のイメージングや定量(例:蛍光免疫染色、フローサイトメトリー)。
- 環境分析: 水質中の微量な汚染物質(例:石油、一部の農薬)の検出。
- 化学・材料科学: 高分子や半導体材料などの特性評価。
- 食品科学: ビタミンや食品添加物などの定量。
蛍光分析は、その感度の高さと選択性の高さから、特に微量分析が求められる分野で非常に重要な役割を果たしています。
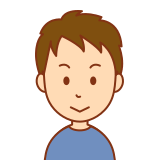
蛍光分析は、物質に励起光を当てた際に放出される蛍光を利用し、微量な成分の種類(定性)や量(定量)を高感度・高選択的に測定する分析手法です。
蛍光分析はなぜ感度が高いのか
蛍光分析が高感度な最大の理由は、測定方法がシグナル(蛍光)の増加分を検出する方式であるため、バックグラウンドノイズの影響を非常に小さくできるからです。これは、吸光分析など他の多くの分析手法と比較することで明確になります。
1. ゼロベースからのシグナル検出 (発光測定)
- 蛍光分析は、試料が光を吸収した後に、自ら発する光(蛍光)を検出します。
- 原理的に、蛍光がない状態(ブランクまたはゼロレベル)は「光のない真っ暗な状態」として扱えます。
- このゼロの状態から、わずかな量の蛍光物質が存在するだけで光の増加分としてシグナルが明確に検出されます。
- つまり、微量な蛍光物質でも、シグナルを明確な増加として捉えることができるため、感度が非常に高くなります。
2. バックグラウンドノイズの低減
- 蛍光の波長は、照射した励起光の波長よりも必ず長くなります(ストークスシフト)。
- この波長差を利用して、検出器の手前でフィルターや分光器を用いて、強力な励起光を完全に遮断できます。
- 励起光を遮断することで、分析の妨げとなる散乱光や迷光といったノイズ(N)のレベルを極めて低く抑えることができます。
- 結果として、シグナル(S)とノイズ(N)の比である S/N比が非常に大きくなり、微量成分から得られる弱いシグナルでも、ノイズに埋もれずに検出できるのです。
吸光分析との違い
一般的な吸光分析(分光光度法)は、以下の理由で蛍光分析ほどの高感度を得ることが難しいです。
| 特徴 | 蛍光分析 | 吸光分析 |
| 測定対象 | 発せられた光の強さ(増加分)を測定する。 | 入射光の減少分(透過率の差)を測定する。 |
| バックグラウンド | 励起光を遮断するため、バックグラウンド(ノイズ)は非常に低い(ゼロベース)。 | 測定には強い入射光が必要であり、その光を基準とするため、バックグラウンドが高い。 |
| 微量測定 | 弱い蛍光でも、ノイズに埋もれずにシグナルとして検出しやすい。 | 非常に低い濃度では、吸収による光の減り具合が小さすぎて、装置のノイズやブランクとの差に埋もれやすい。 |
この原理的な違いにより、蛍光分析は吸光分析に比べて一般的に1,000倍以上の高感度を持つとされています。
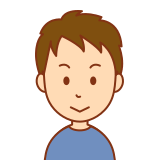
シグナルをゼロベースから検出し、励起光と異なる蛍光の波長を利用して励起光(ノイズ源)を遮断できるため、S/N比が極めて大きく、高感度になります。
励起光を吸収する蛍光団の種類は
蛍光分析で励起光を吸収し、蛍光を発する物質を蛍光団(Fluorophore, 蛍光体)と呼びます。蛍光団の種類は非常に多岐にわたりますが、化学的な構造と用途によって大きく分類できます。
1. 蛍光団の化学的な種類
蛍光団の多くは、電子が非局在化している共役二重結合を多く持つ芳香族化合物や複素環化合物です。これらの構造が光エネルギーの吸収と放出に適しています。
- 単環芳香族化合物:
- 例: ベンゼンやその誘導体(通常は比較的弱い蛍光、励起・発光波長が短い)
- 多環芳香族炭化水素 (PAHs):
- 例: ナフタレン、アントラセン、ピレンなど。環の数が増えるほど励起・発光波長は長くなります。
- ヘテロサイクリック化合物(複素環化合物):
- 窒素(N)や酸素(O)などのヘテロ原子を含む環状化合物です。
- 例: キニーネ、リボフラビン(ビタミンB2)、インドール環(タンパク質中のトリプトファンなど)。
- キサンテン系色素:
- 非常に強力な蛍光色素群。
- 例: フルオレセイン (Fluorescein) や ローダミン (Rhodamine) 誘導体。生命科学分野で広く使われます。
2. 生体分子そのもの
特定の生体分子は、それ自体が蛍光団として機能します。
- アミノ酸:
- タンパク質を構成するアミノ酸のうち、トリプトファン、チロシン、フェニルアラニンは紫外光を吸収し、蛍光を発します。特にトリプトファンの蛍光はタンパク質の構造解析によく利用されます。
- 補酵素・ビタミン:
- 例: NAD(P)H(還元型ニコチンアミドアデニンジヌクレオチド)、FAD(フラビンアデニンジヌクレオチド)、リボフラビンなど。これらは代謝経路の研究に利用されます。
3. 分析・バイオ分野で使用される代表的な蛍光色素
分析やイメージングの目的で人工的に開発された蛍光プローブ(蛍光色素)は、その用途や励起/発光波長の領域で分類されます。
| 分類 | 代表的な例 | 特徴・用途 |
| 青色蛍光色素 | DAPI, Hoechst (ヘキスト) | DNAに結合し、核染色に用いられる。励起波長が短く、UVに近い。 |
| 緑色蛍光色素 | FITC (フルオレセインイソチオシアネート) | 最も古くから使われる色素の一つ。免疫染色や細胞トレーシングに利用される。 |
| 橙〜赤色蛍光色素 | Texas Red, Cy3, Rhodamine | 緑色や黄色光で励起される。光安定性(褪色しにくさ)に優れるものが多い。 |
| 近赤外蛍光色素 | Cy5, Alexa Fluor 647, IRDye | 波長が長いため、生体試料の自家蛍光(ノイズ)や光散乱の影響を受けにくく、深部のイメージングに適しています。 |
これらの蛍光団は、抗体や核酸などの特定の分子に結合(標識)させることで、目的の生体分子を可視化したり、定量したりするために広く用いられています。
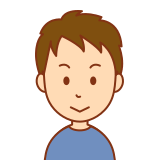
芳香族化合物(ナフタレン、アントラセンなど)、複素環化合物(キニーネ)、キサンテン系色素(フルオレセイン、ローダミン)、および生体分子(トリプトファン、NAD(P)H)など、共役二重結合を持つものが蛍光団となります。
蛍光分析で測定できない物質の例は
蛍光分析は高感度ですが、世の中のほとんどの物質は、それ自体では蛍光を発しないため、そのままでは測定できません。測定できない物質は、主に以下の2つのパターンに分類できます。
1. 蛍光を放出しない物質(本質的に蛍光団ではない物質)
蛍光を発する分子(蛍光団)は、多くの場合、共役二重結合を持つ芳香族化合物や複素環化合物に限られます。この構造を持たない多くの物質は蛍光を発しません。
- 単結合のみで構成された有機化合物:
- 例: アルカン(メタン、エタンなど)、アルコール(メタノール、エタノールなど)、糖類など。
- 単純な無機化合物:
- 例: 食塩 などのイオン性化合物、水、二酸化炭素 など。
- 多くの金属イオン:
- 溶液中の多くの金属イオンは、ウランやタリウムなどのごく一部を除き、それ自体は蛍光を発しません。
- 単純なアミノ酸:
- タンパク質を構成するアミノ酸のうち、トリプトファンなど一部を除いたほとんどのアミノ酸(例:グリシン、アラニン)は、そのままでは蛍光が非常に弱いか、検出できません。
2. 蛍光を放出しても検出が困難な物質
物質によっては光を吸収し励起状態になりますが、蛍光を放出する以外の方法でエネルギーを失ってしまうため(非放射失活や消光)、測定が難しい場合があります。
- 強い電子吸引性基を持つ化合物:
- -COOH(カルボキシ基)、-NO2(ニトロ基)、重いハロゲン(臭素、ヨウ素)などが分子に含まれていると、エネルギーが熱として失われやすくなり、蛍光が著しく弱くなる(消光)か、ゼロになる傾向があります。
- 溶存酸素などの影響を受けやすい物質:
- ナフタレンやアントラセンなどの蛍光団は、溶液中の溶存酸素によって蛍光強度が低下する(消光現象)ため、測定には脱気などの煩雑な前処理が必要になることがあります。
測定できない物質を測定する方法
蛍光を発しない物質でも、分析のニーズがあるため、以下の方法で間接的に測定可能にすることが一般的です。
- 蛍光誘導体化:
- 測定したい物質(例:アミノ酸や脂肪酸)に、蛍光を発する蛍光試薬(プローブ)を化学的に結合(誘導体化)させ、蛍光性を持つ化合物に変換してから測定します。
- 蛍光性錯体の生成:
- 蛍光を発しない金属イオンに、有機蛍光試薬を作用させて蛍光性を持つ錯体を生成させ、その錯体の蛍光を測定します。
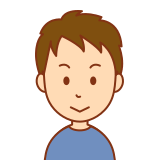
共役二重結合を持たないアルコールや糖類、単結合のみの有機化合物、および単純な無機化合物(NaClなど)は、それ自体が蛍光を発しないため、そのままでは測定できません。


コメント