この記事で分かること
- イオン化方法の種類:質量分析法におけるイオン化は、分析対象の分子に電荷を与え、気相状態にする工程です。主な手法に、電子を直接ぶつけるEI法(低分子向き)、溶液を噴霧するESI法、レーザーを使うMALDI法(高分子向き)などがあります。
- 壊れ方が固有な理由:分子内の結合エネルギーは場所ごとに異なり、電子の衝撃を受けると「切れやすい場所」から優先的に壊れるからです。生成される断片の安定性や組み換えパターンも構造に依存するため、物質固有の「指紋」となります。
- 電気的に安定していられる構造とは:陽イオンのプラス電荷を、周囲の炭素や電子が分散して補える構造です。特に3級カチオンのような枝分かれが多い構造や、ベンゼン環の隣などの共鳴が起こる場所、窒素等の隣は安定し、強いピークとして現れます。
質量分析法のイオン化方法と類似物質の見極めかた
機器分析とは、化学反応を用いる古典的な化学分析に対し、物質が持つ物理的・化学的性質を精密な機器で測定し、その物質の成分や構造を分析する方法の総称です。
高感度で迅速な分析が可能であり、微量な成分や複雑な混合物も精度高く分析できるため、現代の科学技術分野で広く利用されています。
今回は、質量分析法のイオン化に関する記事となります。
質量分析法とは
質量分析法とは、物質を原子・分子レベルでイオン化し、その質量と数を測定して成分を特定する手法です。「分子の重さを測る超精密な天秤」のようなもので、微量な試料から物質の同定や定量、構造解析が可能です。
質量分析のイオン化はどのように行われるのか
質量分析(Mass Spectrometry: MS)におけるイオン化は、分析したい試料分子に電荷を持たせ、気相状態にするプロセスです。
磁場や電場を用いて分子を分けるには、まずその分子が「イオン(電気を帯びた状態)」である必要があるため、これは装置の心臓部とも言える非常に重要な工程です。
試料の性質(揮発性、熱安定性、分子量の大きさなど)によって、いくつかの代表的な手法を使い分けます。
1. 電子衝撃法(EI: Electron Ionization)
最も古典的で標準的な方法です。ガス状の試料に高速電子をぶつけて、分子から電子を弾き飛ばします。
- 仕組み: 加熱したフィラメントから放出された電子を試料に衝突させます。
- 特徴: エネルギーが強いため、分子がバラバラに壊れやすい(フラグメンテーション)。この「壊れ方」のパターンが指紋のように決まっているため、データベース照合による物質の同定に非常に適しています。
- 向いているもの: 低分子、揮発性物質。
2. エレクトロスプレーイオン化法(ESI: Electrospray Ionization)
現代のバイオ分析や製薬で最も多用される手法の一つです。
- 仕組み: 試料溶液を細いノズルから高い電圧をかけながら噴霧します。液滴が小さくなる過程で溶媒が蒸発し、最終的にイオンが空気中に放出されます。
- 特徴: 「ソフトな」イオン化と呼ばれ、分子を壊さずにイオン化できます。また、一つの分子に複数の電荷がつく「多価イオン」を生成するため、タンパク質のような巨大な分子も測定可能です。
- 向いているもの: タンパク質、アミノ酸、薬物代謝物(液体クロマトグラフィー LC との相性が抜群)。
3. マトリックス支援レーザー脱離イオン化法(MALDI: Matrix-Assisted Laser Desorption/Ionization)
ノーベル賞を受賞した田中耕一氏らの研究でも有名な手法です。
- 仕組み: 試料を「マトリックス」という光を吸収しやすい物質と混ぜて結晶化させ、そこにレーザーを照射します。マトリックスがエネルギーを吸収して爆発的に気化する際、試料分子を道連れにしてイオン化させます。
- 特徴: ESIと同様にソフトなイオン化で、非常に大きな分子(高分子やポリマー)を壊さずに測定できます。
- 向いているもの: 高分子化合物、タンパク質、バイオイメージング。
イオン化法の使い分けまとめ
| 手法 | 衝撃の強さ | 主な対象 | 特徴 |
| EI | 強い (ハード) | 低分子・ガス | 構造解析、ライブラリ検索に強い |
| ESI | 非常に弱い (ソフト) | 中〜高分子・液体 | LCと直結可能、多価イオンが出る |
| MALDI | 弱い (ソフト) | 高分子・固体 | レーザー使用、ポリマー分析に強い |
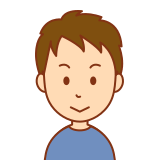
質量分析のイオン化は、分析対象の分子に電荷を与え、気相状態にする工程です。主な手法に、電子を直接ぶつけるEI法(低分子向き)、溶液を噴霧するESI法、レーザーを使うMALDI法(高分子向き)などがあります。
なぜ壊れ方は物質ごとに固有なのか
物質ごとに「壊れ方(フラグメンテーション)」が固有である理由は、分子の化学構造によって「結合の強さ」が場所ごとに異なるからです。
強いエネルギーが加わると、分子の中で相対的に弱い結合から優先的に切れていきます。
固有性が生まれる3つの要因
- 結合エネルギーの違い分子を形作る共有結合には、切れやすい場所と切れにくい場所があります。例えば、炭素同士の単結合よりも、二重結合や特定の官能基(アルコールやアミノ基など)の周辺は、特定のパターンで切れる性質があります。
- 生成物の安定性分子が切れた後、バラバラになった断片(フラグメント)が「電気的に安定していられるか」が重要です。より安定な構造を持つ断片が、結果として多く検出されます。
- 転位反応単に切れるだけでなく、分子内で原子が移動して組み換わる(転位)こともあります。この複雑な組み換えパターンも、分子の立体的な構造に依存します。
同じ材料(原子)を使っていても、設計図(構造)が違えば、ハンマーで叩いた時の壊れ方は変わります。この「壊れた破片の重さと量のバランス」をグラフ化したものがマススペクトルであり、いわば分子の指紋のような役割を果たします。
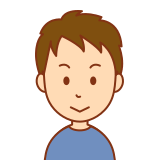
分子内の結合エネルギーは場所ごとに異なり、電子の衝撃を受けると「切れやすい場所」から優先的に壊れるからです。生成される断片の安定性や組み換えパターンも構造に依存するため、物質固有の「指紋」となります。
メタンとエタンを質量分析するとどのように分解されるのか
メタン(CH4)とエタン(C2H6)を電子衝撃法(EI)で分析すると、それぞれの分子構造に応じた固有の断片(フラグメント)が生じます。
それぞれの壊れ方と、特定の手順を見てみましょう。
1. メタン(CH4)の場合
メタンは最も単純な構造なので、水素が1つずつ取れていくパターンになります。
- m/z 16: 分子から電子が1個抜けたもの(CH4+。これを分子イオンと呼び、元の重さを示します。
- m/z15: 水素が1つ取れたもの(CH3+。これが最も多く検出されるピーク(ベースピーク)になることが多いです。
- m/z 14, 13…: さらに水素が外れた断片。
2. エタン(C2H6)の場合
エタンは炭素が2つあるため、メタンとは全く異なる重さの場所にピークが現れます。
- m/z 30: 分子イオン(C2H6+)。エタンそのものの重さです。
- m/z 28: 水素が2つ取れてエチレンのような形になったもの(C2H4+)。エタンではこのピークが非常に強く出ます。
- m/z 15: 炭素間の結合が切れて、メチル基になったもの(CH3+)。
3. どうやって特定するのか
以下の2つのステップで特定します。
- 「一番重いピーク」を見る: メタンは16、エタンは30付近にピークがあるため、この時点で「元の重さ」の違いから区別できます。
- 「破片のパターン」を照合する: 例えば m/z 28(炭素2つ分)の強いピークがあれば、それは炭素が1つしかないメタンではないと断定できます。
このように、「分子そのものの重さ」と「どうバラバラになったか」の両方を見ることで、似たようなガスでも正確に特定できるのです。
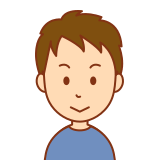
メタン(m/z 16)は主に水素を失い m/z 15 等の破片を生じます。一方、エタン(m/z 30)は C-C 結合の切断や脱水素により m/z 28 や 15 を生じます。この分子重量と破片パターンの違いから両者を特定します。
アイソマー(構造異性体)はどのように見極めるのか
質量分析において、分子式が同じ(重さが同じ)なのに構造が異なるアイソマー(構造異性体)を見極めるには、電子衝撃法(EI)で得られる「フラグメント(断片)のパターンの違い」を詳しく読み解きます。
1. 結合の切れやすさの違い
- n-ブタン(直鎖型): CH3-CH2-CH2-CH3真ん中の炭素結合が切れると、CH3CH2+(m/z 29)というエチル基の断片が強く出ます。
- イソブタン(枝分かれ型): CH(CH3)3中心の炭素からメチル基(CH3)が取れやすいため、M-15 である m/z 43(イソプロピル基)のピークが非常に大きく出ます。
2. 特徴的な転位反応(マクラファティ転位など)
より複雑な分子(ケトンやエステルなど)では、特定の構造を持つアイソマーでしか起こらない「転位反応」があります。特定の配置の水素原子が移動して切断されるため、これにより「枝分かれがどこにあるか」を確実に特定できます。
3. スペクトルライブラリとの照合
実際の実務では、得られたチャートを数十万件のデータが登録された標準ライブラリ(NISTなど)と照合します。類似度(マッチファクター)を算出することで、人間が判断しにくい微細なパターンの違いからアイソマーを判別します。
重さが同じでも「どこが切れやすいか」という構造上の弱点が異なるため、現れるピークの強弱パターンを比較することで見極めが可能になります。
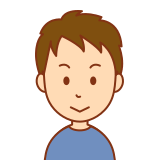
質量分析では、重さが同じでも構造(枝分かれや結合位置)により「切れやすい場所」が異なります。このため、生成されるフラグメント(断片)のパターンが固有の「指紋」となり、これらを比較することでアイソマーを見極めます。
電気的に安定していられる構造とはどんな構造なのか
質量分析において「電気的に安定していられる構造」とは、分子が壊れた後にできる陽イオン(カチオン)が、電荷を分散させて自分の身を守れる構造を指します。
不安定なイオンはすぐにさらに分解されますが、安定な構造を持つ断片は壊れずに検出器まで届くため、スペクトル上で「強いピーク」として現れます。
1. 炭素の置換数(次数)が高い
炭素(C)に結合している他の炭素が多いほど、プラスの電荷が周囲に分散されて安定します。
- 3級カチオン > 2級 > 1級 > メチル基 の順に安定です。
- 先ほどのイソブタン(枝分かれ構造)のピークが強いのは、安定な3級カチオンを作りやすいからです。
2. 共鳴構造が作れる
プラスの電荷が特定の場所に留まらず、広範囲に移動(共鳴)できる構造は非常に安定します。
- ベンゼン環(芳香族): 電荷が環全体に広がるため、非常に壊れにくいです。
- アリル位・ベンジル位: 二重結合やベンゼン環の隣の炭素でプラスが発生すると、電子が流れ込んで助けてくれるため安定します。
3. ヘテロ原子(O, Nなど)の隣
酸素(O)や窒素(N)などの孤立電子対を持つ原子が隣にあると、その電子がプラスを補うように働きます。これを「オクテット則」を満たすための安定化と呼び、アミンやアルコールの分析で特徴的なピークを生みます。
「プラスの電気を、隣の炭素や電子がいかに助けて(分散して)あげられるか」が安定性の決め手です。この安定な構造を知ることで、スペクトルから逆算して元の分子構造を特定できます。
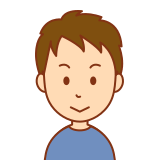
陽イオンのプラス電荷を、周囲の炭素や電子が分散して補える構造です。特に3級カチオンのような枝分かれが多い構造や、ベンゼン環の隣などの共鳴が起こる場所、窒素等の隣は安定し、強いピークとして現れます。


コメント